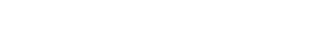Question
- 解雇・退職等
- 残業代請求
- 労働審判(訴訟)
- 団体交渉・
労働組合対応 - 予防法務
(就業規則等) - 労働災害(労災)
対応 - 外国人労働者に
関する法務 - その他労務
トラブル
- 従業員を解雇できるのはどのような場合ですか。
- (狭義の)普通解雇はどのような場合に認められますか。
- 整理解雇はどのような場合に認められますか。
- 懲戒解雇はどのような場合に認められますか。
- 解雇予告手当を支払えば解雇は有効になるのですか。
- 解雇が無効となった場合、従業員に対して何らかのお金を支払う必要はありますか。
- パート・アルバイトなどの非正規労働者は、正社員と比べて簡単に解雇が認められますか。
- 有期雇用契約の従業員は、期間が満了すれば退職してもらうことができますか。
-
- 従業員を解雇できるのはどのような場合ですか。
解雇には、普通解雇と懲戒解雇があります。前者は更に病気や能力不足など会社の経営状態以外を理由とする狭義の普通解雇(以下、単に「普通解雇」ともいいます。)と、会社の経営状態を理由とする整理解雇に分けられます。
どのような場合に解雇が認められるかは、会社としてどの解雇の手段をとるかによっても異なります。
-
- (狭義の)普通解雇はどのような場合に認められますか。
普通解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である場合に限り認められます(労契法16条)。
普通解雇を行う場合については、労働者の労働能力の低下・喪失、勤務態度など一定の類型化が可能ですが、いずれの場合であっても解雇理由が合理的で(客観的合理性)、しかも解雇が相当でなければ(社会的相当性)、解雇は無効となります。
この点、日本の裁判所は、容易には解雇の社会的相当性を認めず、労働者側に有利な諸事情を考慮したり、解雇以外の手段による対処を求めることがあります。また、仮に裁判となった場合には、解雇するに至った事情について、会社の側で具体的に主張立証する必要があります。
どのような場合に、普通解雇が認められるかについては、過去の裁判例や個別の事情を踏まえて判断されますので、普通解雇を考えている方は、まずはご相談下さい。
-
- 整理解雇はどのような場合に認められますか。
整理解雇は、労働者側の事由を直接の理由としたものではなく、会社の側の経営状態を理由とする解雇であるため、(狭義の)普通解雇と比べてより具体的で厳しい制約が課されています。
すなわち、①解雇の必要性(経営上の理由により人員削減をする必要性があるか)、②解雇回避の努力(残業の削減や希望退職者の募集などの手段をとり、当該人員を解雇することを回避するための努力が尽くされていたか否か)、③人選の合理性(勤務成績、勤続年数等を踏まえており、恣意的に解雇の対象者が選ばれていないか)、④手続の妥当性(労働組合や対象の労働者に対して誠意をもって対応をしたか等)という4つの要素を中心に様々な事情を総合的に判断して、解雇の客観的合理性と社会的相当性が認められる場合に整理解雇が認められます。
整理解雇についても、(狭義の)普通解雇と同様、個々の事案について詳しくお話を伺う必要がありますので、まずはご相談下さい。
-
- 懲戒解雇はどのような場合に認められますか。
懲戒解雇は、①懲戒処分ができる場合に該当することが必要で、更に②労働者の行為の性質や態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に当たらないことも必要です(労契法15条)。
①の懲戒処分ができる場合に該当するためには、懲戒の種別と事由を就業規則に記載し、それを周知させておく必要があります。
②については、普通解雇の場合にも同じような要件が必要でしたが、懲戒解雇をする場合には、大抵の場合、退職金の不支給など労働者にとって不利益が大きいため、実際の判断に当たっては普通解雇の場合よりもより厳しい判断されることになるでしょう。
日本の企業の場合、会社の金品を横領したとか、よほどの非違行為でなければ懲戒解雇まではしないことが通常であると思います。懲戒解雇ができる場合には、通常の解雇(普通解雇)の方が認められるケースも少なくないため、どの手段をとるかについては慎重な判断が求められるといえます。
-
- 解雇予告手当を支払えば解雇は有効になるのですか。
なりません。
解雇予告手当の支払は解雇の効力と無関係であり、解雇予告手当を支払ったとしても、正当な理由のない解雇は無効です。
-
- 解雇が無効となった場合、従業員に対して何らかのお金を支払う必要はありますか。
支払わなければならない場合があります。
その一つとしては、解雇が無効とされた期間中の賃金の支払です。
従業員の側に就労の意思や能力がないなどの事情があれば別ですが、解雇が無効となった場合は、従業員が働けなかったのは違法な解雇をした使用者に責任があるとされ、無効とされた期間中の賃金を支払う必要があります。
もう一つとしては、従業員が違法な解雇によって賃金以外にも損害(精神的損害など)を受けたとされた場合には、慰謝料を支払う必要があります。
このように、解雇が無効となった場合には、会社の受ける不利益は極めて大きなものとなりえます。
トラブルにならずに解雇できるかの判断は専門家でないと難しい部分がありますので、まずは相談されることをお勧めします。
-
- パート・アルバイトなどの非正規労働者は、正社員と比べて簡単に解雇が認められますか。
パート・アルバイトだからと言って、正社員よりも解雇がしやすいなどといったことはありません。
パート・アルバイトなどの短時間労働者については、正社員と比べて契約条件が緩やかに定められていることが多いですが、解雇ができるか否かという点では正社員と全くかわらず、解雇権濫用法理などが適用されます。
なお、有期雇用契約の場合には、やむを得ない事由があると認められるときに限って解雇が認められるとされており、これは解雇権濫用法理をより一層厳格にしたものであると解されているので、より一層解雇が難しくなる場合もありえます。
-
- 有期雇用契約の従業員は、期間が満了すれば退職してもらうことができますか。
更新がなされない場合は期間満了により退職となるのが有期雇用の原則です(雇い止め)ので、退職してもらうことは原則として可能です。
しかし、雇い止めが無効とされる場合もあります。
すなわち、①過去何度も更新されている有期雇用契約で、無期雇用と同視できるような事情がある場合(労働契約法19条1号)、または、②労働者が契約更新を期待することについて合理的理由がある場合(同条2号)に、雇い止めが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」(同条柱書)は、雇用契約は従来と同一の条件で更新されたものとみなされますので、期間が満了したものとして退職してもらうことはできません。
- 残業代に時効はありますか。
- 管理職は残業代を支払わなくてよいのでしょうか。
- 従業員に対して、残業をせずに早く帰るよう促しているのですが、これに従わずダラダラと勤務し残業代を請求してくる従業員がいますが、残業代を支払わなければならないのでしょうか。
- 変形労働時間制、フレックスタイム制を導入している場合には残業代を支払わなくてもよいのでしょうか。
- みなし残業制とはなんですか。その場合、残業代を支払う必要はないのですか。
- 残業代の計算方法を教えて下さい。
-
- 残業代に時効はありますか。
あります。
残業代請求権は、賃金請求権の一種です。賃金請求権は、給与支払日から2年間経過すると時効により消滅します(労基法115条)。例えば、平成27年1月分の給与が、1月末日締め、2月25日払いだとすると、給料日の2年後である平成29年2月25日を過ぎることによって、残業代が時効消滅するわけです。
-
- 管理職は残業代を支払わなくてよいのでしょうか。
ほとんどの場合支払う必要があるのが現状です。
労基法上、「管理監督者」(同法41条2号)には残業代を支払わなくてもよいことになっていますが、一般論として、いわゆる管理職のほとんどは、管理監督者には該当しません。
そのため、もし管理職についている従業員から残業代の請求を受けた場合、残業代を支払う必要がある場合がほとんどでしょう。
したがって、会社としては、「管理監督者」に当たる管理職とそうでない管理職を明確に区別しておくべきです。
どのように考えればよいのかについては、会社の事業内容によっても様々ですので、まずはご相談ください。
-
- 従業員に対して、残業をせずに早く帰るよう促しているのですが、これに従わずダラダラと勤務し残業代を請求してくる従業員がいますが、残業代を支払わなければならないのでしょうか。
会社として、従業員に対し帰宅を促しているなどの対応をしなければ、残業代を支払わなければならない可能性が高いです。
残業代は、時間外労働のうち、法律に定められた時間(原則1日8時間、週40時間)を超えた部分の「労働時間」について支払うべき賃金ですが、「労働時間」に当たるか否かは、従業員が使用者の指揮命令下に置かれているか否かで判断されます。
そして、ダラダラと勤務をしていたとしても、残業代稼ぎのためであることが明らかであるなどの事情がない限り、会社内で仕事をしている以上は、指揮命令下に置かれているものであると判断される可能性が高いものと思われます。
-
- 変形労働時間制、フレックスタイム制を導入している場合には残業代を支払わなくてもよいのでしょうか。
変形労働時間制とフレックスタイム制は、ともに法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を柔軟化させる制度ですが、あくまで法定労働時間の枠を変更する制度にすぎないので、一定の枠の範囲内で法定労働時間を超えた場合には、残業代を支払う必要があります。
-
- みなし残業制とはなんですか。その場合、残業代を支払う必要はないのですか。
「みなし残業制」という法律上の制度はありません。
「みなし労働時間制」という制度はありますが、俗に言われる「みなし残業制」というのは、「みなし労働時間制」とは別のものを指していることが大半です。具体的には、「固定残業代制」のことを指している場合が多いと思われます。
「固定残業代制」とは、残業代のうち一定の額を予め固定的な基本給や手当に組み込んで支払う制度です。
このような制度自体は(一定の条件はありますが)適法であり、予め定めた範囲内の残業については、追加で残業代を支払う必要はありません。
しかし、予め定めた範囲を超える残業に対しては、当然に割増賃金を支払う義務が生じます。
例えば、「月の所定労働時間が160時間、基本給が18万5000円で、基本給に残業代20時間分を含む」という契約だったとすると、方程式を使えば、残業代分が2万5000円であることがわかります。
この場合、その月の残業時間が20時間以下であれば、残業代を支払う必要はありません。
しかし、20時間を超えて残業した場合には、超えた分については残業代を支払う必要があるわけです。
-
- 残業代の計算方法を教えて下さい。
(月給制の場合)まず、月給を月あたりの平均所定労働時間で割って基礎時給を出します。
この基礎時給に割増率(単なる時間外労働なら1.25倍)をかけて、残業代単価を出します。
これに残業時間をかけると、残業代を算出することができます。
例えば、月給32万円、月あたりの平均所定労働時間が160時間の労働者が、月60時間の残業(深夜労働、休日労働は無し)をした場合を考えてみましょう。この場合、基礎時給が2000円、残業代単価が2500円ですので、この月の残業代総額は、2500円×60時間=15万円、となります。
-
- 労働審判とはどのような制度ですか。
労働審判とは、解雇、雇止め、賃金不払い、労働条件の変更などをめぐる個別の労働紛争につき、各地方裁判所に設置された労働審判委員会が審理を行う手続きです。
労働審判委員会は、裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名(使用者側、労働者側各1名)で構成されます。
-
- 労働審判の流れを教えて下さい。
労働審判は、原則として3回以内の期日で審理が終結します。
3回の期日の中で、労働審判委員会から調停案が提示されることがあり、労働者と使用者の側で調停案の内容で合意ができれば、その時点で労働審判が終了します。
3回目の期日においても調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審理を終結する宣言をし、労働審判を行うことになります。なお、労働審判の申し立てのうち約8割が調停により解決しているのが実情です。
労働審判は、それまでの期日において提出された証拠や関係者の話を聞いた内容を踏まえて労働審判委員会が下しますが、労働審判委員会が提示した調停案に近い内容にケースが比較的多いです。
労働審判は、当事者のいずれかが2週間以内に異議を申し立てなければ確定し裁判上の和解と同一の効力を有しますので、異議が出なかった場合には当事者は労働審判の内容に従う必要があります。
審判の内容にいずれかの当事者が異議を申し立てた場合には、審判は効力を失い訴訟に移行し、通常の訴訟手続きと同様に審理を続けることになります。
-
- 労働審判と訴訟(裁判)との違いはなんですか。
訴訟は基本的には判決を目指す手続ですが(もちろん途中で和解もできますが)、労働審判は、両当事者の主張立証、裁判所の事実認定・法的判断という訴訟的側面を持ちつつも、可能な限り調停成立を目指す手続です。また、労働審判は迅速を重んじるという点も特徴であり、そのため訴訟と比べ証拠調べ手続が簡略化されている等の違いがあります。さらに、訴訟手続は公開され誰でも傍聴可能ですが、労働審判手続は非公開です。
-
- 訴訟になった場合、解決までの期間はどれくらいですか。
訴訟提起から一審判決まで、6か月~1年程度のケースが多いです。場合によってはもっと長引くこともあり、様々な費用や精神的な負担も大きくなりがちですので、労働者・使用者の双方にとって訴訟による解決は最終手段であり、先に労働審判や示談による解決を目指すことが多いです。
- 団体交渉を申し込まれた場合、必ず応じなければならないのですか。
- 団体交渉を申し込まれた場合、とりあえず交渉の場に出席しておくという対応で問題ありませんか。
- 団交拒否にあたるとされた場合、会社にはどのような不利益が生じますか。
- 団体交渉に応じた結果、最終的に何をするのでしょうか。
-
- 団体交渉を申し込まれた場合、必ず応じなければならないのですか。
労組法上は、使用者側が団体交渉に応じる義務の範囲について直接の規定を設けていませんが、一般的には、①使用者が処分権限を持ち、かつ、②労働条件その他労働者の待遇に関する事項(賃金、労働時間、採用・解雇、福利厚生等)、又は労使関係の運営に関する事項(団体交渉・労使協議のルール、争議行為の手続等)については義務的団交事項と呼ばれ、団体交渉に応じる義務があると解されています。
義務的団交事項はこのようにかなり広く、実際に団体交渉を申し込まれた場合には、上記のいずれかに該当する可能性が高いので、経営者としては、団体交渉を申し込まれた場合、とりあえず団体交渉に応じることを前提とした方がよいでしょう。
-
- 団体交渉を申し込まれた場合、とりあえず交渉の場に出席しておくという対応で問題ありませんか。
使用者は、団体交渉に形式的に応ずるだけではなく、誠実に交渉する義務(誠実交渉義務)を負うと考えられているため、形式上は団体交渉に応じたとしても合意達成の意思が全くないような態度で団体交渉に臨んだ場合には、誠実交渉義務違反となる可能性があります。
そのため、使用者側としては、自分の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなど、誠意ある対応をとる必要があります。
仮に誠実交渉義務に違反する場合は、実質的な団交拒否(労組法7条2号)として、不当労働行為に当たります。
ただし、上記の誠実交渉義務は、合意の成立そのものを義務付けるものではありませんので、使用者として誠実に対応しても合意に達せず、交渉が行き詰まりに達した場合には、使用者は交渉を打ち切ることができ、その場合は不当労働行為は成立しません。
-
- 団交拒否にあたるとされた場合、会社にはどのような不利益が生じますか。
①不当労働行為に対しては、労働組合は労働委員会へ救済を申立て(労組法27条以下)をすることができ、労働委員会において申立てに理由があると判断されれば、団交への応諾や交渉における誠実な対応などの是正措置が発せられます。これに応じなければ、50万円以下の過料に処されます(32条)。
②また、会社の団交拒否を労働関係調整法上の労働争議(労調法6条)と捉えて、労働委員会にあっせん等の申請がされる可能性があります(平均して2か月程度かかりますが、場合によってはそれ以上手続きに付き合わなければなりません)。
③さらに、裁判所に対し団体交渉を求める地位の確認という形で仮処分の申立てをされることも考えられます。仮処分の手続は迅速性が要求されており、対応を迫られることになります。
④加えて、団交拒否によって損害が生じた場合には、不法行為(民法709条)として損害賠償請求を受けることもあり得ます。
-
- 団体交渉に応じた結果、最終的に何をするのでしょうか。
会社と労働組合の間で交渉を続けた結果、ある事項について合意した場合、労働協約が締結されることになるのが自然な流れです。なぜなら、労働協約は、書面で作成し、かつ、両当事者が署名または記名押印をすることによってはじめて効力を生じるからです。団体交渉の結果合意した事実について書面を作成しなかった場合、裁判例上は、効力が否定されていますので、きちんとした形で書面を取り交わす必要があります。
-
- 就業規則を作成するメリットは何ですか。
まず、前提として、事業場単位で常時10人以上の労働者(アルバイトやパートも含みます)が働いている場合には、就業規則の作成・届出の義務があります。
もっとも、10名未満であっても、次のようなメリットがあるため、就業規則を作成しておくべきです。
すなわち、就業規則を作成することで、①労働者を採用する際、個別に労働条件について交渉して労働契約書を作成する必要がない、②一定の基準により労働条件が決まることにより、労働者ごとの労働条件を確認する必要が減り、労働者の管理が容易となる、③懲戒事由等を就業規則に定めておくことにより、懲戒処分をすることが可能になる(裏を返せば、就業規則に懲戒事由等の定めがない場合には、懲戒処分をすることができないということです)といったメリットがあります。
このうち、10人未満の会社であれば①②で得られるメリットはそれほど大きくないようにも思えますが、小規模であり使用者と労働者との距離が近いがゆえに個別の交渉が難航し、その結果個別の労働条件が複雑になってしまうこともあります。就業規則を作成しておけば、このような事態も避けることができます。
-
- 期間を限定して労働者を雇いたいのですが、注意するポイントはありますか。
平成24年に改正された労契法18条により、有期労働契約が更新されて通算契約期間が5年を超える場合に、労働者が期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換を申込みをしたときには、自動的に期間満了日の翌日から無期労働契約が成立することになりました。
使用者としては、無期労働契約への転換を回避するために、通算契約期間が5年を超える前に有期労働契約者を雇止めにするという対応をとることが考えられます。
例えば、1年契約の労働者に対して4回を限度とする契約更新限度を定めをしておき、通算契約期間が5年を超えないようにしておくなどです。
もっとも、契約書上このように定めていたとしても、労働者に対して契約の更新がされることを期待させるような言動や対応を使用者側が行っていた場合には、当然に雇用契約を終了させることができない(実際には、雇用契約上の地位にあるなどとして賃金の請求をされるといった形で紛争となることが多いでしょう)ため、使用者側としてはこの点の注意が必要です。
-
- 残業代の請求を避けるために使用者が事前にとれる方法は、どのようなものがありますか。
残業代の請求を避けるために使用者側が事前に取り得る方法としては、①残業の事前許可制、②変形労働時間制、③フレックスタイム制、④固定残業代制の各制度の導入が考えられます。
その他には、一定の要件を満たす場合には、⑤事業場外労働のみなし制、⑥専門業務型裁量労働制、⑦企画業務型裁量労働制などを導入することも考えられますが、基本的には①~④の中で検討していくということになるでしょう。
このうち、④固定残業代制は、残業代のうち一定の額を予め固定的な基本給や手当に組み込んで支払う制度であり、近年ではこの制度を活用する会社が増えています。
ただし、残業が比較的少ない会社では④固定残業代制は一定の額を上乗せして基本給や手当に組み込むため、結果として総支給額が増えてしまい、①残業の事前許可制等の方が適切な対策である場合もあります。
具体的にどのような対策をとるべきかについては、会社の規模、会社の就労の実態などに即して判断する必要がありますので、まずは専門家にご相談下さい。
- 従業員が就業時間中にけがをして休業し、労災申請をするので証明書を出してほしいと求めてきました。これに協力すると、何か会社にデメリットはありますか?またデメリットがあった場合それを避けることはできますか。
- 業務中に社員が労働事故によって負傷し、休業しました。労災認定がなされ休業・療養していたのですが、休業が長期にわたったことから、復帰を促したところ、当面復帰は困難との回答がなされました。いつまでも復帰を待って人員を補充せずにもいられないので、やむを得ず解雇しようと考えていますが、可能でしょうか。
- 工場で労災事故が起こり、従業員が怪我をしました。会社は労災申請に協力し、労災認定がなされて当該従業員は休業していたのですが、会社に対して、安全配慮義務違反で損害賠償請求を提起してきました。どのように対応すればいいでしょうか。
- 従業員が心臓疾患で急死した後、家族が、過労死によるものだから労災申請をしたいといってきました。この様な場合にも労災は認定されるのでしょうか。また、会社は申請に協力しなければならないのでしょうか。
- 従業員が、上司のパワハラによってうつ病になったので、労災の申請をしたいといってきました。この様な場合にも労災は認定されるのでしょうか。また、会社は申請に協力しなければならないのでしょうか。
-
- 従業員が就業時間中にけがをして休業し、労災申請をするので証明書を出してほしいと求めてきました。これに協力すると、何か会社にデメリットはありますか?またデメリットがあった場合それを避けることはできますか。
労災事故が発生した場合、事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりませんが、労災保険に加入して労災認定がなされると、労災保険による給付が行われ、その範囲で事業主は労働基準法上の補償責任を免れ(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補 償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)、会社に直接の経済上の不利益は発生しません。
そもそも労災かどうかは、労働基準監督署が認定する事で、会社は事故の事実を証明するだけですし、仮に会社がこれを拒んでも、労働者は自ら手続きを実行でき、会社が労災認定を回避する事はできません。
また、労災認定がなされても、それは、当該労災事故に業務遂行性、業務起因性が認められるとの判断がなされただけであり、会社の故意・過失が認定されるわけではありません。
労働者が労災の申請をすると、場合によっては労働基準監督署の立ち入り検査がなされる可能性もありますが、通常の労働災害ならその可能性は高くないですし、会社が手続きに協力しないからと言って、回避できるものでもありません。
また、労災事故の発生率が高い会社では、「メリット制」と言って保険料率が上昇しますが、対象となるのは100人以上の従業員を有する会社(若しくは一定の条件を満たす20人以上の従業員を有する会社)です。
労災事故が疑われる場合は、会社は労働者死傷病報告書を提出し(労働安全衛生規則第97条)、従業員の手続きに協力する義務があり(労災保険法施行規則第23条)、違反した場合は「労災隠し」として行政罰・刑事罰(労働安全衛生法第120条、122条)が定められていますので、不明な事があれば労働・労災問題に精通した当事務所にご相談ください。
-
- 業務中に社員が労働事故によって負傷し、休業しました。労災認定がなされ休業・療養していたのですが、休業が長期にわたったことから、復帰を促したところ、当面復帰は困難との回答がなされました。いつまでも復帰を待って人員を補充せずにもいられないので、やむを得ず解雇しようと考えていますが、可能でしょうか。
労働基準法第19条は、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間については解雇してはならない」と定めており、当該社員が療養中及び、復帰後30日間は解雇できません。
ただし、労働基準法第81条の規定により、療養開始後3年を経過し、会社が平均賃金の1,200日分の打切補償を支払う場合は解雇ができます。
また、傷病が重い場合、休業から1年半以降、労働基準監督署の職権により休業補償給付から傷病補償年金に移行しますが、休業給付療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合や傷病補償年金を受けることになった場合は、打ち切り給付を行ったものとして、解雇できます。
-
- 工場で労災事故が起こり、従業員が怪我をしました。会社は労災申請に協力し、労災認定がなされて当該従業員は休業していたのですが、会社に対して、安全配慮義務違反で損害賠償請求を提起してきました。どのように対応すればいいでしょうか。
労災保険給付は,慰謝料は対象としておらず,休業損害や逸失利益の全額を補償するものではありませんので、労災認定がなされ、労災保険からの給付がなされても、会社に安全配慮義務違反やその他の故意・過失があり、労働者がそれによって労災保険給付を超える損害を受けている場合は、会社はその損害を補償しなければなりません(逆に言えば、同一の事由については,労働者が労災保険から給付を受けた場合、その価額の限度において民法の損害賠償の責を免れることになります(労基法84条2項類推))。労働事故が起こった場合は、上記の様に損害賠償の請求を受ける場合がありますので、直ちに事故が起こった状況を可能な限り正確に記録するとともに、従業員の疾病の状況についても、協力が得られる限りで把握しておくことが望まれますので、労働・労災問題に精通した当事務所にご相談ください。
-
- 従業員が心臓疾患で急死した後、家族が、過労死によるものだから労災申請をしたいといってきました。この様な場合にも労災は認定されるのでしょうか。また、会社は申請に協力しなければならないのでしょうか。
厚生労働省の基準によると、業務による明らかな過重負荷を受けた事により発症した脳・心臓疾患は業務上の疾病として取り扱われることとされており、①異常な出来事 ②短期間の過重業務 ③長期間の過重業務 のいずれかが原因で脳・心臓疾患が発症したと判断された場合には、労災認定がなされます。
①②③の存在については、厚生労働省の基準が定められており一定の判断が可能ですが、最終的にそれが原因で脳・心臓疾患が発症したといえるか否かは、医学的要因も含んだ総合判断に委ねられ、一概に決める事はできません。会社側としては、申請書の「災害の原因及び発生状況」には、確認できた事実(○○月の間、平均□□時間の労働をし、虚血性心疾患で死亡した等)を記載すれば十分で、従業員の主張する因果関係を記載する必要はありません。また事実関係すら食い違うようであれば、証明書は記載しないという選択も已むを得ません。
その場合も従業員は労災申請が可能であり、申請がなされれば、労働基準監督署による調査がなされます。また労災申請と同時に、民事の賠償請求がなされる可能性もあります。
会社側としては、従業員からその様な申し出があった時点で、民事訴訟に備える意味でも迅速に事実関係の調査を行い、労働と発症した疾患との間に因果関係がないのであれば、的確にそれを主張する必要があります。労働・労災問題のみならず医療訴訟にも精通した当事務所にご相談ください。
-
- 従業員が、上司のパワハラによってうつ病になったので、労災の申請をしたいといってきました。この様な場合にも労災は認定されるのでしょうか。また、会社は申請に協力しなければならないのでしょうか。
厚生労働省の基準によると、①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと の3つが満たされる場合、精神疾患に対しても労災認定がなされます。しかしながら、業務による強い心理的負荷の存否や、これが精神疾患発症の直接の原因となったか否かは、立証以前にその線引きが難しい問題です。会社側としては、申請書の「災害の原因及び発生状況」には、確認できた事実(○○が上司として指導に当たり、部下である□□うつ病を発症した等)を記載すれば十分で、従業員の主張する因果関係を記載する必要はありません。また事実関係すら食い違うようであれば、証明書は記載しないという選択も已むを得ません。
その場合も従業員は労災申請が可能であり、申請がなされれば、労働基準監督署による調査がなされます。また労災申請と同時に、民事の賠償請求がなされる可能性もあります。
会社側としては、従業員からその様な申し出があった時点で、民事訴訟に備える意味でも迅速に事実関係の調査を行い、パワハラ等の事実がないのであれば的確にそれを主張する必要があります。労働・労災問題のみならず精神衛生にも精通した当事務所にご相談ください。
- 外国人を雇用する場合、入管法(出入国管理及び難民認定法)上どのような制限がありますか?また、その制限に抵触しない事は、どのようにしたら確認できますか。
- 日系人には就労制限はないのですか。
- 外国人労働者にも最低賃金を支払わなければなりませんか。
- 外国人労働者も、社会保険に加入しなければなりませんか。
- 外国人留学生を、アルバイトとして雇用する事はできますか。
- 外国人を雇用した場合、どの様な届出が必要ですか。
- 不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、不法就労外国人とは知らずに雇用した場合、「罰則」が適用されますか。
-
- 外国人を雇用する場合、入管法(出入国管理及び難民認定法)上どのような制限がありますか?また、その制限に抵触しない事は、どのようにしたら確認できますか。
日本に在留する外国人は、入国の際に定められた在留期間に限って、与えられた在留資格の範囲内で就労が認められます。したがって、外国人を雇用する場合は、①在留期間を過ぎていないか②就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、を確認する必要があります。
これらの在留期間や在留資格は、在留カード、パスポート紙面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により確認できます。
不明な点がありましたら、外国人雇用問題に精通した当事務所にご相談ください。
-
- 日系人には就労制限はないのですか。
入管法において、日系二世、三世については、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認められ、これらの資格で入国した場合、在留期間の制限はありますが、その活動には制限がありません。したがって、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格で入国した日系人には就労制限はなく、単純労働分野での就労も可能です。
ただし、日系人であっても他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格の範囲内での活動に制限され、例えば「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できません。
-
- 外国人労働者にも最低賃金を支払わなければなりませんか。
外国人労働者も日本人の労働者と全く同じく労働基準法をはじめとする労働諸法令の適用があり、最低賃金を支払わなければなりません。技能実習生も同様です。最低賃金を支払わなかった場合、差額の支払いだけでなく、最低賃金法違反により50万円以下の罰金の罰則が科せられます。
-
- 外国人労働者も、社会保険に加入しなければなりませんか。
日本の社会保険には、①労災保険 ②雇用保険 ③厚生年金・健康保険(両者はセット)があります。どの保険も加入義務に日本人・外国人の区別はありません。
①は原則一人でも雇用した事業者には保険料の納付が義務付けられる強制保険で、仮に不法就労であっても納付義務があります。
②は日本人・外国人の区別はありませんが、一定の条件のアルバイト・パート、全日制の教育機関に通う学生(留学生)、ワーキングホリデーの外国人などは対象外になります。
③も日本人・外国人の区別はなく、常時雇用か否かや、就業時間等によって、日本人と同様の加入義務があります。
-
- 外国人留学生を、アルバイトとして雇用する事はできますか。
留学生は、入国管理局に申請して、資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトができます。
資格外許可を受けると、パスポートに許可証印が押されているか、又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、留学生を雇用しようとする場合は確認して下さい。
留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあたっては、1日8時間以内)。
なお、資格外活動の許可を受けなかったり、規定の時間を超えてアルバイトをした場合は不法就労となり、留学生が強制送還、在留資格の更新拒絶等の処分を受けるだけでなく、使用者(店長等現場管理者を含む)も不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)で罰せられますので十分に気をつけて下さい。
-
- 外国人を雇用した場合、どの様な届出が必要ですか。
外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際には、その都度、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出る必要があります。ハローワークへの届出を怠ったり,虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金を科せられます。
-
- 不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、不法就労外国人とは知らずに雇用した場合、「罰則」が適用されますか。
「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」には、不法就労助長罪(入管法73条の2)により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられ、又は、これらが併科されます。この「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」には、法人、法人の代表者、現場責任者などが該当します。
不法就労であるとはっきりと認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するなど、知らないことに過失があった場合も処罰の対象となりますので、外国人労働者を採用するに当たっては、在留カード、パスポート紙面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により「在留資格」「在留期間」を確認し、少しでも不明な点があったら外国人雇用問題に精通した当事務所にご相談ください。
-
- 従業員の賃金をカットしたいのですが、どのようにすれば賃金をカットできますか。
賃金は労働者の労働条件の中でもっとも重要な労働条件であるので、労働者の同意を得なければ賃金のカットをすることは原則としてできません。
ただ、同意を得なければ全く認められないかと言われれば必ずしもそうではなく、就業規則の変更による方法(複数の労働者の賃金カット)や、減給の方法(個別の賃金カット)によって認められる余地があります。
前者については、労契法10条に定めがあり、就業規則を周知させていることを前提に、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして合理的なものであると言えるときに賃金をカットできます。
後者については、減給が就業規則などにあらかじめ定められており、当該減給措置が違法な差別や権利濫用に当たらないような場合に認められる可能性があります。減給措置がなされるケースとしては、職務や職位の変更に伴う場合と、年棒制など能力や成果の評価に基づいて(職務や職位は変更されないまま)賃金が減額される場合があります。
-
- 賃金カットをするには他には手段はないのですか。
実質的な意味で賃金をカットする方法としては、①残業規制、②ベア、定昇の停止、③賞与の額の調整があります。
まず①については、法律上労働者には残業する権利はないので、残業をせず帰宅を促すことによって総支給額を減らすことができます。ただし、残業をすることがやむを得ないにもかかわらずそれを認めないという措置は違法であり、割増賃金のみならず、付加金をも支払わなければならない場合もあり、更にいえば刑事告発の例もありますので、注意が必要です。なお、就業規則等に残業保障等の規定がある場合には、別途考慮が必要です。
②については、ベアや定昇については、就業規則等に定めがなければ使用者の裁量により自由に行うことができ、仮に定めがある場合であっても、賃金の減額と比べて労働者の不利益性は低いと考えられますので、賃金カットが認められにくいような場合でもベア、定昇の停止は認められる余地があります。
最後に、③についてですが、法律上賞与の支払は義務ではないので、就業規則等に定めがない限りは、使用者の裁量によって不支給とすることが可能です。
-
- 始業・終業時の着替え時間についても賃金を支払う必要がありますか。
賃金を支払う必要があるのは費やした時間が労働時間に該当する場合です。そして、どのような時間が労働時間に当たるかは、一般的には労働者が使用者の指揮命令下にあると客観的に評価できるか否かによって判断されます。
始業・終業時の着替え時間について労働時間に該当するかはケースバイケースであり、裁判例上は、労働時間であることを肯定した事例と否定した事例の両方が存在します。
指揮命令下にあるかどうかは、義務付け(強制の程度)、業務性の有無(業務との関連性)、時間的・場所的拘束性の有無など様々な要素を個別のケースごとに考慮して判断されるため、具体的な事案でどう判断されるかについては、専門家に相談されることをお勧めしますが、抽象的に言えば、事業所内で(場所的拘束)、朝礼の開始5分前までに(時間的拘束)、仕事着(業務関連性)への着替えをすることを義務付けている(強制の程度)ような場合には、労働時間に当たると言いやすくなります。
お悩みは解決しましたか。
解決しない場合は
直接ご相談下さい。
CONTACT
お問い合わせ
お急ぎの方は、お電話でのご相談もお待ちしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。


 0120-741-783
0120-741-783